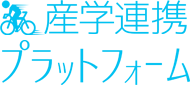-
 千葉大学
千葉大学反射・発光表示可能なデュアルモードディスプレイの研究
1.明所では反射型、暗所では発光型の表示を可能とする新規表示デバイス。 2.溶液塗布型で容易、安価に製造できる。- 研究者
- 大学院融合科学研究科 中村 一希 准教授
- キーワード
- 電子ペーパー、デジタルサイネージ、携帯端末アプリ
-
 千葉大学
千葉大学触媒の未来を切り開く絶え間のない挑戦
1.高効率な触媒の提供 2.高収率な触媒の提供 3.副生成物の少ない高純度な触媒の提供- 研究者
- 大学院工学研究科 佐藤 智司 教授
- キーワード
- 各種工業製品用触媒
-
 千葉大学
千葉大学熱電変換材料及びその製造方法
新エネルギーの利用法の一つとして熱と電力を相互に変換できる材料熱電変換材料は、一部実用化されているものの、低融点であり、BiやTe等希少・有害な元素が使用されている。本技術は、より高温で使用できる高性能熱電変換材料とその製造方法を提供する。本技術の電変換材料は、Ti1-xCrxOz (0<x <0.5、0< z <0. 1 3) の組成からなることを特徴とする。- 研究者
- 大学院工学研究科 魯 云 教授
- キーワード
- 高効率電気材料の製造、エネルギー供給
-
 千葉大学
千葉大学合成開口レーダーセンサを利用する環境・防災・インフラ監視技術
土砂崩れ、道路の陥没、橋梁等公共建設物の劣化等を一早く検知し、早急に修復することは安全面からも経費の節約の面からも重要である。本研究では人工衛星、航空機、無人航空機等に車載による探査と画像提供により、広範囲、高速的、効率的なデータ提供を行う。- 研究者
- 環境リモートセンシング研究センター
- キーワード
- 公共物の点検、インフラ整備、道路・路面の観測、ガスパイプの監視、高圧送電線鉄塔土台の変位観測等
-
 千葉大学
千葉大学循環型社会の構築を目指した、廃棄物の有効利用・再資源化システム・環境浄化技術
21世紀に入り、エネルギー、水、食料、鉱物資源などの資源問題や人類の活動に伴う地球環境問題が重要な課題となっている。本研究では、循環型社会の構築を目指し、廃棄物の有効利用・再資源化システムや環境浄化技術の開発に取り組んでいる。- 研究者
- 大学院工学研究科 和嶋 隆昌 准教授
- キーワード
- 循環型社会の構築を目指した廃棄物の有効利用・再資源化システム、環境浄化システム
-
 千葉大学
千葉大学データ重ね合わせプログラム及びデータ重ね合わせ方法
より容易に、二つの三次元データ群(点群データ)を融合することのできるデータ重ね合わせプログラム及びデータ重ね合わせ方法を提供します。この技術によって、森林バイオマスの評価に必要な樹木の幹部データを詳細に取得することが可能になります。- 研究者
- 大学院 園芸学研究科 加藤 顕 助教
- キーワード
- 二つの三次元データ群、データ重ね合わせプログラム、森林バイオマス
-
 千葉大学
千葉大学比較的低温で再生可能な二酸化炭素吸収材
室温付近で水蒸気が共存しても邪魔されずに選択的にCO2を吸収でき、かつ、材料の再生温度が低い(従来200℃、目標100℃以下)安価なCO2吸収材。- 研究者
- 大学院理学研究科 加納 博文 教授
- キーワード
- 工場排気やビル空調における二酸化炭素(CO2)吸収(除去)材、化学的CO2固定材、CO2運搬用材料、CO2 ケミカルヒートポンプ
-
 千葉大学
千葉大学ナノ結晶性セラミックスの合成
コンデンサは、スマホ等の半導体基板に多数使われており、その大きさはイチゴの種よりも小さい。それでも更に小型化が求められており、それに伴い誘電体層の薄化、誘電体(例:チタン酸バリウム)粒子の微小化が求められている。本研究の狙いは、機能を保持したままの微小化にある。- 研究者
- 大学院理学研究科 大場 友則 准教授
- キーワード
- セラミック、チタン酸バリウム、誘電体材料、誘電体層、電極層、積層セラミックコンデンサ、原料セラミック微粒子、圧電素子、PCTサーミスタ(温度上昇に対して抵抗が増大)、光学用樹脂改質材
-
 千葉大学
千葉大学ヨウ素-ポリビニルアルコール(PVA)錯体画像の光形成
1.これまでにはない光照射部分が発色するPVA-ヨウ素錯体フィルムを実現。 2.簡便な画像形成プロセス。- 研究者
- 大学院融合科学研究科 高原 茂 教授
- キーワード
- マーキング記録フィルム
-
 千葉大学
千葉大学透明・黒・ミラー及び多色状態を可能にする調光素子
1.エレクトロクロミック素子として、透明/黒状態/鏡面(ミラー)/赤/青/黄色)以上の発現が可能。 2.溶液塗布型で容易、安価に製造できる。- 研究者
- 大学院融合科学研究科 小林 範久 教授
- キーワード
- スマートウインドウ、デジタルサイネージ、防眩ミラー、電子ペーパー、携帯端末アプリ
-
 千葉大学
千葉大学3次元構造色材料
ポリドーパミンをシェルとする独自のコア-シェル粒子を利用することで視認性の高い構造発色を実現。- 研究者
- 大学院工学研究科 桑折 道済 准教授
- キーワード
- コロイド粒子、3次元、構造色、コア-シェル、ドーパミン、不退色
-
 千葉大学
千葉大学ケミカルヒートポンプによる未利用熱エネルギーリサイクル利用システム
各種廃熱や太陽熱等の未利用エネルギーを化学的に蓄え、改質し、外部エネルギーを必要とせずに冷熱・温熱としてリサイクル有効利用する 各種ケミカルヒートポンプシステム。- 研究者
- 大学院工学研究科 小倉 裕直 教授
- キーワード
- 化学蓄熱、ケミカルヒートポンプ、廃熱、太陽熱、冷熱、温熱、リサイクル、省エネ、CO2 削減、コスト削減、サスティナブル