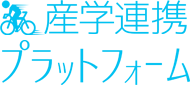-
 国立環境研究所
国立環境研究所排水処理の大幅な低炭素化に寄与するメタン発酵技術の開発と実用化
適用排水の種類が限定されるなどの理由で導入が遅れていたメタン発酵排水処理技術ですが、研究開発を通じて適用可能な排水の有機物濃度や温度の下限が大幅に拡大されました。本技術は、食品系の産業のみならず、 電子産業など種々の産業排水処理の低炭素化に寄与します。- 研究者
- 地域環境保全領域 副領域長 珠坪一晃
- キーワード
- 排水処理、メタン発酵、省エネルギー、エネルギー回収
-
 国立環境研究所
国立環境研究所定点撮影による生態系モニタリング技術
時々刻々と変化する生態系の観測は多くの労力と危険が伴い、人的な観測では範囲や頻度も限られてしまいます。そこで効率的な生態系の観測を可能とするため、市販品のカメラやビデオなどを活用した無人観測システムと解析手法を開発しています。- 研究者
- 生物多様性領域 室長 小熊宏之
- キーワード
- 気候変動、フェノロジー、自動撮影、深層学習、無人観測、分光特性
-
 国立環境研究所
国立環境研究所高磁場MRIでのヒト脳内含水量分布測定法
高磁場MRIを用いて、非侵襲にヒト脳内の含水量分布を測定する方法を開発しました。高磁場MRIでは、高周波磁場(B1)の不均一性のため、外部標準の利用が出来ません。これを解決して、ヒト脳内の含水量を定量化し、イメージングする方法です。- 研究者
- 環境リスク・健康領域 領域長 渡邉英宏
- キーワード
- 高磁場MRI、ヒト脳、含水量、高周波磁場、B1+、 B1-、不均一性
-
 国立環境研究所
国立環境研究所安価で省力的な光センサーを応用した飛翔生物の自動撮影モニタリング技術
安価で省電力な電子部品等を用いて、棒にとまる性質のある飛翔生物を自動撮影する装置の開発・応用に関する研究を行っています。赤トンボ類などを例に、省力的、非破壊的な生物調査手法の発展を目指しています。- 研究者
- 福島地域協働研究拠点 主任研究員 吉岡明良
- キーワード
- 生き物調査、自動撮影、カメラトラップ、無人観測、非破壊モニタリング
-
 国立環境研究所
国立環境研究所ヒト脳内神経伝達物質の非侵襲測定法
MRIでは、非侵襲に、脳内で代謝により産生される各種アミノ酸を測定することが出来ます。しかし、従来の方法では、ピークのオーバーラップの問題があり、検出が困難でした。この解決のため、ヒト脳内の興奮性神経伝達物質グルタミン酸と抑制性の神経伝達物質GABA(γ-アミノ酪酸)のピークを検出できる方法を開発しました。グリア細胞(アストロサイト)に多く存在するグルタミンも検出が可能です。- 研究者
- 環境リスク・健康領域 領域長 渡邉英宏
- キーワード
- 1H MRS、ヒト脳、非侵襲、神経伝達物質、グルタミン酸、GABA 、グルタミン
-
 国立環境研究所
国立環境研究所ナノプラスチックの環境リスク研究のための標準粒子の作製
球状ナノスケール粒子を6種の汎用ポリマーについて作製する技術です。界面活性剤等の不純物となりうる物質の添加が不要であり、一般的なプラ製品と同等のポリマー分子量、結晶化度、融点等を持つ粒子の作製が可能です。ナノプラスチックの環境リスク研究における標準粒子としての活用を目指しています。- 研究者
- 資源循環領域 研究員 田中厚資/資源循環領域 主幹研究員 鈴木剛
- キーワード
- ナノプラスチック、標準物質、ナノ粒子、汎用樹脂
-
 国立環境研究所
国立環境研究所次世代エアロゾルライダを用いた大気エアロゾルモニタリング技術
PM2.5など大気中の微小粒子(エアロゾル)を対象に、その成分や濃度の鉛直分布を計測する次世代エアロゾルライダ(高スペクトル分解ライダ)手法を開発しています。黒色炭素や黄砂など多様なエアロゾルを低コストで長期的にモニタリングするため、マルチモードレーザーと走査型干渉計を用いた特許技術を導入しています。- 研究者
- 地球システム領域 主任研究員 神慶孝/地球システム領域 室長 西澤智明
- キーワード
- 大気エアロゾル、PM2.5、高スペクトル分解ライダ
-
 国立環境研究所
国立環境研究所バイオガス施設における環境汚染物質の挙動予測モデル
バイオガス化技術を使って、発生するガスを使った発電等のエネルギー利用だけでなく、残渣の固形分や液分の農地還元や資材化まで行う有機性廃棄物のリサイクルの取組が進んでいます。原料となる廃棄物には様々な異物に由来する環境汚染物質が含有され、残渣にも残留することを確認しています。健全なリサイクルを担保するため、実験や調査に基づきそういった汚染物質の施設内における挙動モデルを作成し、プロセスの適正制御による汚染リスクの低減を目指しています。- 研究者
- 資源循環領域 副領域長 倉持秀敏/資源循環領域 主幹研究員 小林拓朗
- キーワード
- バイオガスプラント、環境汚染物質、モデル、リサイクル
-
 国立環境研究所
国立環境研究所生態系を活かした気候変動適応と生態系の機能評価
気候変動に適応するため、生態系の機能を活かした適応策(EbA)に着目が高まっています。国立環境研究所では、気候変動適応にも寄与する生態系の機能評価の研究を進めています。気候・気象条件の不確実性が増す将来に向け、社会・金融技術 × 生態工学技術によるEbA推進策を目指して私たちと協働してみませんか。- 研究者
- 気候変動適応センター 室長 西廣淳
- キーワード
- Nbs、EbA、グリーンインフラ、適応、サンゴ礁、里山、生物多様性
-
 山口大学
山口大学植物微生物燃料電池
グリーンで安全な持続可能エネルギー源の探索は世界中で喫緊の課題です。微生物燃料 電池(MFC)の使用は、細菌の活動を通じてグリーンエネルギーを得る主要な方法の1つと して知られています。微生物燃料電池は、微生物の代謝活動によって緑色の電気を生成で きる生化学的プロセスです。このプロセスでは、細菌が有機物の分解中に電子を放出し、 外部回路が電子を捕らえて電気を生成します。この現象を応用し、生きている植物が発生 させる有機物を用い、微生物燃料電池を通じて生物電気を得ることを植物微生物燃料電池 (PMFC)と呼びます。本研究では、高効率で使いやすいPMFCの開発を行っています。- 研究者
- 工学部 アジズル モクスド 准教授
- キーワード
- 植物微生物燃料電池、グリーンエネルギー
-
 東京都立大学
東京都立大学表面処理剤
有機系の樹脂材料に対する表面処理剤 ポリエチレングリコールを含む界面活性剤様化合物に注目し、 疎水部としてステロイド基を有し、親水部としてポリエチレングリコール を含む化合物が、タンパク質吸着抑制効果を示すことを見いだした- 研究者
- 都市環境学部准教授教授朝山 章一郎 川上 浩良
- キーワード
- バイオマテリアル(生体機能材料)、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、医用高分子、遺伝子、生理活性Zn2+、バイオ医薬品、生体適合性
-
 量子科学技術研究開発機構
量子科学技術研究開発機構イオンビーム育種で害虫防除に役立つ微生物を開発
イオンビームを糸状菌に照射することで、生物農薬の実用化の場面で必要となる殺菌 剤や高温への耐性を持った変異体を作出することができました。- 研究者
- 量子ビーム科学部門上席研究員大野豊
- キーワード
- 生物農薬 微生物 変異体